未経験の私が気づいた、IT導入の落とし穴と“経営”との接点
 mitchei4
mitchei4「ITコンサルティングのチャレンジ」について調べてみました!
はじめに
本日は、ITコンサルティング業務に関わる中で、クライアント企業が直面している「IT導入に伴う財務的リスク」と「経営との整合性の重要性」について深く学びました。私は元々ITに関して全く知識がなかった主婦ですが、この仕事を通して、単なる技術の導入では済まない複雑な背景や構造、そして本質的な課題を感じるようになりました。今日の気づきは、単に業務の一環ではなく、家族の将来や生活にも密接に関わってくる大切な視点だと実感しています。
見えていない「財務リスク」と「経営戦略とのズレ」が最大の障害
企業がIT導入を進める際に最も見落としがちなのは、「導入後の財務的負担」と「経営戦略との整合性の欠如」であり、それらが最終的に失敗に直結するケースが非常に多いということを学びました。特にスタートアップとの連携においては、技術的な革新性だけでなく、企業の現実的な体力と中長期的な視点が欠かせません。
📌 なぜそれが問題なのか?
今日、私が担当した資料整理の中で、過去にIT導入に失敗した複数の事例報告を読み込む作業がありました。その中には、中小企業がAIやクラウドといった先端技術に惹かれて急いで導入を決めたものの、運用コストが予想以上にかさみ、短期間で撤退を余儀なくされたケースが少なくありませんでした。
ある報告書には、営業支援システム(SFA)を導入した企業が、定期的なアップデートとサポート費用に年間数百万円単位の支出を強いられ、初期投資を含めたROI(投資対効果)を3年以内に回収できなかったことが記されていました。
ITは便利で効率的というイメージが先行しがちですが、実際には多くの「見えないコスト」や「人的リソースの調整」が発生します。
導入前の段階でこれらを正確にシミュレーションできていなかったことが失敗の主因でした。
💡 実例から得た気づき:現場と経営、どちらの視点も必要
特に印象に残ったのは、ある製造業の企業が在庫管理システムをクラウドベースのスタートアップ企業から導入した事例です。当初は在庫回転率を改善し、業務効率化を図ることが目的でした。しかし、既存の紙ベースの管理からいきなり高度なITツールへの移行が進められたため、現場スタッフの混乱が大きく、教育コストも想定を上回るものとなりました。
さらに、スタートアップ企業側も大手のようなサポート体制が整っておらず、現場の問い合わせに対応できずに時間だけが過ぎ、結局半年後にシステムは使用停止に。導入費用と教育のための支出が重なり、翌年の設備投資が見送られるという影響まで出ていたのです。
このように、IT導入が他部門の予算配分にも波及するという“経営全体への影響”を軽視していた点が、最大の問題でした。
🎯 改めて感じたこと:本当に必要なのは「全体を見通す視点」
この失敗から得られる教訓は、ただ「便利そうだから導入する」のではなく、企業の中長期的な計画の中でその技術がどのような位置づけになるのかを見極め、経営陣と現場の両方を巻き込んだ意思決定が不可欠であるということです。
私たちが担うべき役割は、そうした“橋渡し”を担い、全体最適を図る視点を持つことだと理解しました。
✅ 再確認:限られた資源を活かす“主婦目線”も大切な視点
このように、IT導入を成功させるには「見える課題」だけでなく、「見えないリスク」、特に財務・人材・時間という資源の配分に深く目を向け、組織全体の成熟度と整合させることが求められると学びました。
主婦として家庭内のやりくりを日常的に行っている自分にとって、この“限られた資源を最大限に活かす”という考え方は、非常に馴染み深く、共感できるものでした。
まとめ
今日学んだことは、ITコンサルティングという仕事が、単なる技術提供にとどまらず、クライアントの事業全体、ひいては経営者のビジョンや現場の価値観まで含めて提案を行う、非常に人間味のある仕事だということでした。私はまだまだ知識も経験も未熟ですが、だからこそ客観的に課題を見つめる視点や、わからないことを「調べる」「聞く」「理解しようと努める」という行動が強みになるのではないかと思っています。
家族の生活を守りながら働く私にとって、「子供の才能を伸ばし、夢を追いかける環境」をつくるためには、安定したキャリアと自己成長の両立が欠かせません。今の仕事で得た学びは、ただ仕事のためではなく、家族のためにもなると信じています。
どんなに小さなことでも、自分の学びが誰かの助けになるように、明日からも一つ一つの業務に丁寧に取り組んでいきます。

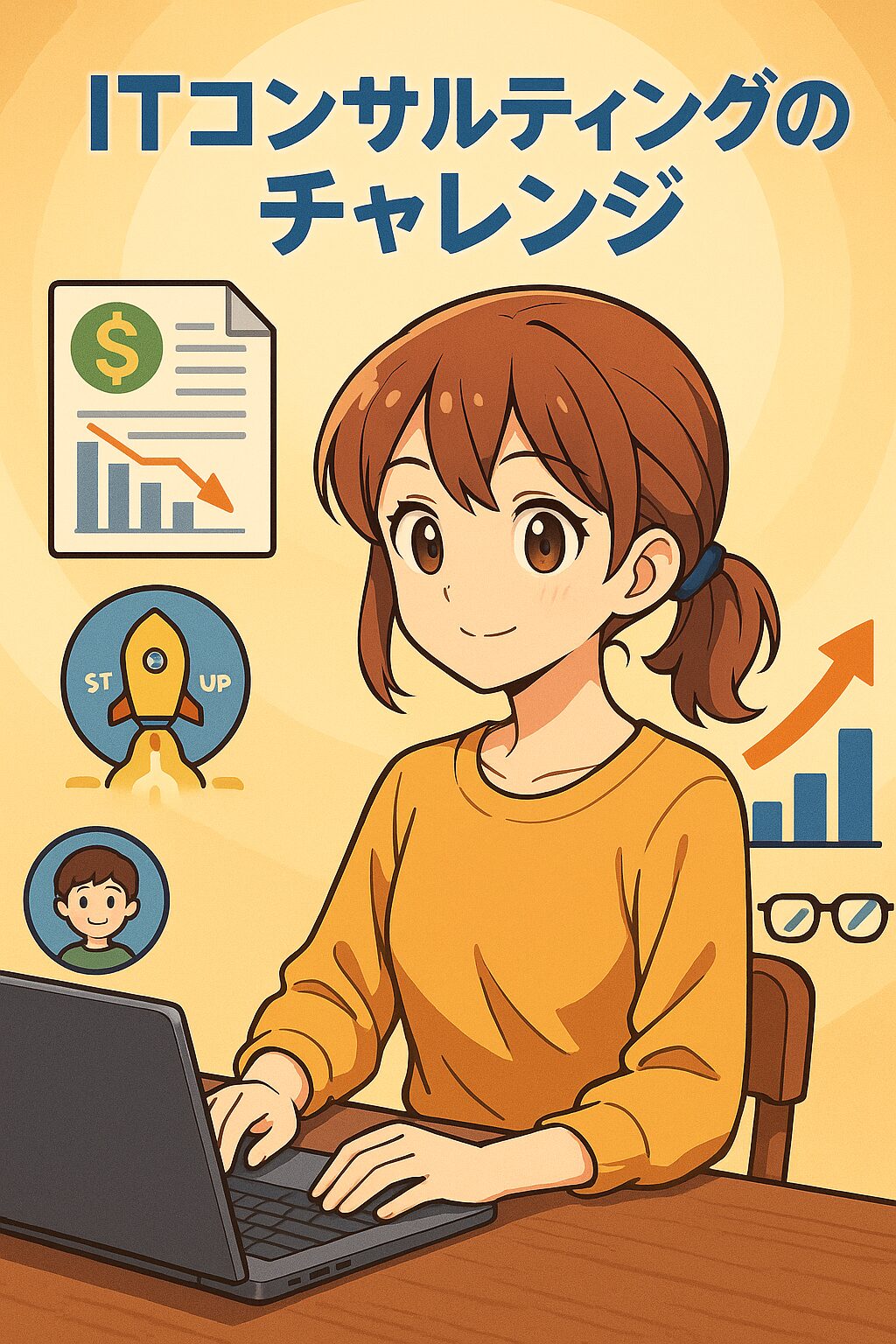
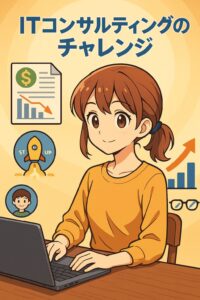
コメント